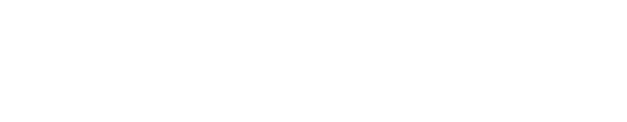-
防除トピックス
無人航空機による病害虫防除の現状と課題(その1)
―空中散布に思うことー ○航空防除の歴史 航空防除は、病害虫や雑草防除の過酷な労働作業からの解放、効率的な病害虫防除に多大な貢献を果たしてきました。 昭和30年代に有人ヘリによる航空防除がはじまり、約30年たった平成の初めころに無人ヘリの事業化がはじまりました。さらに、約30年たった平成28年ころからマルチローター(いわゆるドローン..
続きを読む »
-
防除トピックス
無人航空機による病害虫防除の現状と課題(その2)
○技術上の課題 今や、スマート農業の普及や、みどりの食料システム戦略における化学農薬50%削減(リスク換算)の目標に向けて、マルチの利用が脚光を浴びています。 マルチの長所は無人ヘリより安価なことに加え、軽くて持ち運びが容易なこと、マイドローンであれば防除したい時にいつでも散布できることです。 一方で、いくつかの課題があります..
続きを読む »
-
寅次郎の農薬つれづれ記
満州帝国 北興化学とは
満洲国の歴史を知るには、”満洲回顧集刊行会(会長岸信介)”発行の全928ページ「ああ満州(国つくり産業開発者の手記)」は必読の書である。 この本の”研究と教育・試験場の項”で、元東京都害虫専技の白浜賢一さんが、満洲の公主嶺農試の熊岳城分場で同僚だった西圭一さんについて、戦後引き揚げて北興化学を興こしたことを記述している。戦後派の一般..
続きを読む »
-
寅次郎の農薬つれづれ記
新天地・満洲国 森繫久彌の回顧エッセイ
”満洲回顧集刊行会(会長岸信介)”発行の「ああ満州(国つくり産業開発者の手記)」に満洲電電公社で名アナウンサーとして活躍した森繫久彌のエッセイが記載されている。 もともと戦争嫌いで1939年に赤紙を受け取ったが耳の手術を受けた直後だったので即時帰郷となった。翌1940年、応召されず海外赴任できる数少ない仕事を探しNHKのアナウン..
続きを読む »
-
寅次郎の農薬つれづれ記
蒋介石の日誌
最近コクヨのキャンパスノートの小型が売れている。岸田総理がこのノートに政治問 題を記述していることが話題になった。今回のサッカーのW杯で試合中に森保監督が記録していたノートも同じ物であった。 この種のジェスチャーで以前、政治評論家の竹村健一が黒い手帳を振りかざして「日本の常識は世界の非常識」などと論じていたことを思い出す。岸..
続きを読む »
-
防除トピックス
モモヒメヨコバイ
モモヒメヨコバイは中国、台湾,韓国、北朝鮮に発生が確認されており、うめ、もも、おうとう、あんず、はなうめ、はなももを加害することが知られています。 日本では沖縄県での分布は確認されていましたが,2019年に和歌山県で確認された以、降現在まで、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、..
続きを読む »
-
防除トピックス
ホウレンソウケナガコナダニ
ほうれんそうを加害するコナダニ類は数種類知られていますが、多いのはホウレンソウケナガコナダニです。本種は20数年前から全国的に問題となり、北海道、本州で分布が確認されています。きゅうり、すいか、ピーマン、トマト、ねぎ、にんじん、キャベツ、とうもろこし等多くの作物に寄生しますが、中でも被害が深刻なのがほうれんそうです。 ホウレンソ..
続きを読む »
-
私の自然手帳
カメラ
―眼となりてメモリーとなりて我がカメラ― 今持ち歩いているカメラは、ポケットに入るカード大のものと一眼レフ型の少し重たいものの2つである。カード大のものは旅行に行くときや隣町まで行く時など、腕時計のような感覚でバッグに入れてゆく。一眼レフ型の方は、出かける前から草花や鳥などを写すつもりで肩にかけてゆく。いずれもディジタルで自動焦..
続きを読む »
-
私の自然手帳
探 鳥
―琴弾くや天皇陛下のお出ましぞ― 冬の野山は淋しい限りである。雪国であれば真っ白な世界に埋もれ、ひたすら春を待つばかり。さすがにここ南関東では雪に埋もれることはないが、山はスギやシイなどの常緑樹を除いて、落葉樹はすっかり裸になって、山肌は斑な剥げ坊主のよう。地上では薄茶色に枯れてカサカサに乾いた草の広がりばかりとなる。目をひく花..
続きを読む »
-
私の自然手帳
駆け足の春
―ライオンのごとく春は来るといふ― 緯度は日本よりはるかに高く、サハリンあたりに位置する同じ島国のイギリスには、「3月はライオンのようにやって来て子羊のように去る」という諺がる。一日のうちで雪や雨があったかと思うと晴れ間が出るなど激しく目まぐるしく天候が変わることを言っている。日本でもこの時期三寒四温といわれるように、同じように..
続きを読む »
-
防除トピックス
バイオスティミュラント
農林水産省は2021年5月に「みどりの食料システム戦略」を策定しました。その中で 2050年までに化学農薬の使用量の50%削減(リスク換算)と有機栽培面積を25%拡大することが明記され、その実現手段の1つに、革新的作物保護技術の開発の防除資材としてバイオスティミュラントの利用が例示されています。 バイオスティミュラントとは バイオスティミ..
続きを読む »
-
防除トピックス
サツマイモ基腐病
●被害が拡大し、さつまいもが高騰 最近テレビで「旬の味覚 さつまいもにある異変 価格高騰 農家を悩ませるある問題」などと報じられました。原因はサツマイモ基腐病で、一番成長期の夏場に全国的に長雨が続いたのと、高温だったことで多くのところでイモの腐れが発生し不作になり、価格の高騰につながったとのことです。 ●2018年に沖縄県で初めて..
続きを読む »
-
いまさら聞けない農薬の話
適用表の中の使用回数
家庭菜園愛好家から農薬の適用表をみて「使用回数とは何ですか?一日の散布回数?ハンドスプレーに入っている薬剤ならばハンドルを押す回数ですか?」という質問がありました。 果樹などの永年性作物を含めて一年のうちの生育シーズンに散布できる回数の合計であることを説明はしましたが、農薬使用初心者であれば抱く疑問かもしれません。 作物残留基..
続きを読む »
-
生き物あれこれ(雑草)
ヒルガオ科雑草
朝顔につるべとられてもらい水」、夏の花の代表、朝顔は観賞用としては江戸時代からもてはやされたようです。今では家庭園芸の楽しみの一つ、あるいは小学生の教材になっています。 アサガオの仲間はヒルガオ科で観賞用あり、そこから抜け出して雑草化したもの、帰化雑 草様々です。観賞用のルコウソウは江戸時代に持ち込まれたそうですが、マルバルコ..
続きを読む »
-
生き物あれこれ(雑草)
マメ科雑草
だいず、あずき、そらまめ、えんどうなどの豆は重要な食物ですが、この仲間にも雑草として頑張っているものがあります。そのひとつ芝生などで邪魔なホワイトクローバーいわゆるシロツメクサです。もともとは飼料、緑肥作物、カバークロップとして栽培されて、この場合は貴重な作物ですが、発生してほしくないところに出てきたら雑草です。アカツメクサい..
続きを読む »
-
生き物あれこれ(雑草)
イネ科雑草
世界の高等植物は約20万種といわれ、その中の雑草種は3万種以上になると言われています。それでも作物生産に経済的に被害を与えるものは200種程度との説があります。 日本国内の雑草種は水田、畑あわせて約100種、これに最近では帰化雑草が増え、また除草剤抵抗性雑草の出現もあって増えつつあります。 雑草の種類をその姿、植物分類のからイネ科雑草..
続きを読む »
-
いまさら聞けない農薬の話
有機栽培に使える農薬
農家はJAS規格の有機栽培、家庭菜園では無農薬栽培がおこなわれています。その背景に「農薬は危ない悪者」との考えがあります。 有機栽培でも必要に応じて農薬が使えるように、農林水産省では有機農産物の日本農林規格として使用できる防除資材を次のように規定しています。農薬として登録されているものも含まれます。少し長くなりますが列挙します。 ..
続きを読む »
-
いまさら聞けない農薬の話
適用作物の作物群
農薬使用の際、守らなければならない項目はいくつかあり、これまでにもこの欄で述べてきています。 守るべき項目の中で適用作物はまさにトップにあるのではないでしょうか? しかし、使用者には作物名を見ただけでは戸惑うこともあります。対象としている作物が適用表の中にあるのだろうか?似たような名前だけど、適用作物になるのだろうか? 作物残..
続きを読む »
-
生き物あれこれ(害虫)
「ヒアリ」と「沈黙の春」
原産地は南米中部 ヒアリは毒を持ち「世界の侵略的外来種ワースト100」に指定されています。 元々は南米中部に生息していたアリですが、船や飛行機に積まれたコンテナや貨物にまぎれ込んで、1940年代頃からアメリカ合衆国やカリブ諸島に次々と侵入し、2000年代には原産地から遠く離れたオーストラリア、ニュージーランド、中国、台湾でも発見されるよ..
続きを読む »
-
生き物あれこれ(害虫)
タバココナジラミのバイオタイプ
農作物を加害するコナジラミ類は、オンシツコナジラミ、タバココナジラミ、ツツジコナジラミなどが知られていますが、話題の多いのはタバココナジラミのバイオタイプです。 ●タバココナジラミのバイオタイプとは タバココナジラミは世界的に分布し、形態的には区別できませんが、寄主植物や生物的特徴が異なる20以上のバイオタイプが知られています..
続きを読む »
最新ニュース
農薬の深イイ話
- ホーム
- 農薬の深イイ話